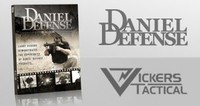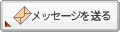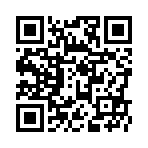2008年05月22日
Insurgency war

旧南アフリカ陸軍 第32大隊(アンゴラ内戦初期、宗主国ポルトガル側勢力として戦い、敗戦を機に南アへ亡命した部隊を母体としています)
ハイ!あふりかです。
日本のミリタリーファンの興味の対象って圧倒的に「アメリカ軍」の人気が高いですよね。
WW2ファンにはドイツ軍の人気が根強いですが現用となると米軍装備の方が非常に多いです。
ですんで私、かなりのマイノリティで御座います。パラベラムは「PMC」というミリタリーをカテゴライズした場合、非常に新しい分野に焦点を当てていますが、調べれば調べる程に「アフリカ」との関連を強く感じます。
キーワードは「Insurgency war」
Insurgencyは「暴動、反乱」を意味しますが、あふりかは「不正規戦」と意訳しています。
米軍系列の本では使われる事が少ないのですが、英軍に関連する洋書で盛んに使用されています。
 冷戦下の低劣度紛争として真っ先に頭に浮かぶのは「ベトナム戦争」でしょう。TVが映し出した初の戦争として現在でも当時の映像を見る事が出来ますし、様々な映画が作られましたから「知名度」は抜群、情報量も多いです。現用でも人気のグリーンベレーやSEALsが投入されたので、ここが起源と考えられがちですが、それらの特殊部隊がモデルとしたのはSASやWW2のLLDGなどの英軍特殊部隊です。
冷戦下の低劣度紛争として真っ先に頭に浮かぶのは「ベトナム戦争」でしょう。TVが映し出した初の戦争として現在でも当時の映像を見る事が出来ますし、様々な映画が作られましたから「知名度」は抜群、情報量も多いです。現用でも人気のグリーンベレーやSEALsが投入されたので、ここが起源と考えられがちですが、それらの特殊部隊がモデルとしたのはSASやWW2のLLDGなどの英軍特殊部隊です。大英帝国は海外領地を多く抱えていたために反乱などへの対処に度々軍を派遣していました。派遣地域は世界規模、主に南半球が多く、熱帯、乾燥帯での戦いが多く、敵対勢力も点在する少規模グループでしたので、大規模正規軍では対応が出来ません。そこで編み出されたのが能力の高い小規模部隊による対反乱戦Insurgency warであったわけです。
 英軍がInsurgency war戦術を確立したのはマラヤ紛争であると言われています。投入されたのはSAS。
英軍がInsurgency war戦術を確立したのはマラヤ紛争であると言われています。投入されたのはSAS。SASは拠点をゲリラが活動するジャングルへ移し小人数によるパトロールを頻繁に行い敵対勢力の行動を押さえ込んでいきます。また地域住民へ医療行為を施すなの人心掌握に努め、村自体を防御拠点とするなどし地域住民と密接な関係をつくり、ゲリラ情報を得易い状況とします。脱線しますがAR15は米軍よりも早くSASによってマラヤ紛争で使用されました。
SASがマラヤで行った戦術が、後に米グリーンベレーがベトナム戦争で行った「ハーツ &マインズ」「戦略村」のモデルとなった手法です。初期GBメンバーが、英国特殊部隊が残した戦訓の多くを取り入れ製作したマニュアルは代々隊員に引き継いで行きます。
ダメだ、長すぎますね。続きます。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。